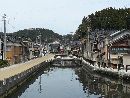|
能登町(歴史)概要: 能登町には石仏山遺跡と呼ばれる古代自然崇拝の痕跡が残る地域で、石仏山自体が神聖視され山麓には「前立」、「唐戸」、「奥立」と呼ばれる巨石群によって祭場が形勢、現在でも例祭が行われ信仰の対象になっています。
延長5年(927)に編纂された延喜式神名帳に記載されている式内社神目伊豆伎比古神社(現在神目神社)が創建されるなど当地域にも大和朝廷の支配下となり中世に入ると万福寺や松岡寺などの寺院も建立されました。
室町時代に入ると幕府の管領だった畠山氏が能登国の守護職となり文明6年(1474)には当主畠山義統の2男棚木左門氏が棚木城、3男松波義智が松波城を築き、奥能登の支配を固め、城麓には城下町が整備されました。
特に松波城には枯山水の庭園を設けるなど京都の文化と取り入れています。天正5年(1577)、上杉謙信の能登侵攻により両城共に落城し上杉領となりましたが謙信の死によって上杉領が大きく後退し変わって織田信長の支配となります。新たに領主となった前田利家は国人領主だった長連龍を遣わし不穏因子を掃討し能登を掌握、江戸時代に入ると加賀藩に属しています。
能登町・歴史・観光・見所の動画の再生リスト
|